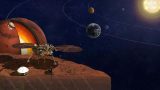先日NASAのジェット推進研究所が金星を上空から観測するための熱気球の実験を行いました。
空の上から何を観測するのかというと地質についてです。
……おや?と思った人もいるかと思います――なぜ地質調査を上空からするのかと。
それは金星が、人間はおろか機械であっても生存が難しい灼熱の地獄だからです。
惑星としての金星の特徴や過去の調査などを振り返りつつ、NASAの挑戦する新たな試みを紹介します。
金星――分厚い二酸化炭素で覆われた灼熱の地獄
 Image Credit:NASA/Jet Propulsion Laboratory-Caltech
Image Credit:NASA/Jet Propulsion Laboratory-Caltech
金星は昔から明るい星として知られていました。
その輝きは女性に例えられ美の象徴として描かれるようになります。
金星は地球とほぼ同じ大きさであり、また当時の観測技術では金星の地表を確認できなかったため、人々の想像力はさらに加速していきました。
一部の天文学者は金星には水がないことを指摘していましたが、大衆はそんなことはお構いなしに金星への憧れを抱くようになります。
1950年代頃までは植民地の候補になったり、宇宙旅行の行き先として数えられたりしました。
またSF作家などが宇宙人のいる星として描いたこともあり、金星のイメージは人々にとってごく身近で親近感すら抱かせる存在でした。
しかし1960年代に始まったソビエトのベネラ計画やアメリカのマリナー計画などにより、次第に金星の全容が明らかになってきます。
金星を覆う大気が二酸化炭素でできていること、地表が温室効果のため高温であること、そして高い気圧のためにとても人間が住めるような場所ではないことなどがわかってきました。
これまでに考えられていたような牧歌的なイメージは崩れ去り、反対に恐怖にも似たものに変わっていきます。
そして1970年にソビエトのベネラ7号が初めて金星の地表に着陸すると、そこが平均500度以上の灼熱地獄であることが判明します。
(着陸したベネラ7号は想定以上の熱さのため当初の予定よりもだいぶ短い23分間で通信が途絶してしまいました)
これらの事実により金星に対するイメージは決定的に変化しました――金星とはまさに地獄の星でした。
こうして金星は宇宙旅行の行き先リストから外れましたが、科学者や天文学者たちはますます金星の内側について興味を抱くようになります。
金星の内部はアメリカが1989年に打ち上げた金星探査機マゼランによって、初めてその詳細が明らかになりました。

上の画像は金星探査計画の一つパイオニア・ヴィーナス計画で金星をレーダー調査したパイオニア・ヴィーナス・オービターとマゼランの調査データから起伏を強調して作成した金星の地表図です。
なんとなくゲームにでてくる全体マップのような感じもしますが、これはあくまで上空からのレーダーによる調査です。
これまでに実際に地表に到達した探査機は全て短時間で機能を停止しているため、本格的な地表や地質についての調査は進んでいません。
しかしそんな熱い場所にわざわざ行って地質を調査することになんの意味があるのでしょう。
古くから金星は地球の兄弟星として考えられてきました。
太陽からの距離は、地球がおよそ1億5000万km、金星がおよそ1億800万km、その差は宇宙の観点からすると微々たる距離です。
しかしなぜこの似たような2つの星がこれほど違う運命をたどったのか――それを知ることができれば地球が特別な星である理由の解明につながります。
また金星を知ることは、太陽系の他の惑星がどのようにしてできたのかについての新しい見方を提供します。
2018年の11月に火星探査機インサイトが無事火星に着陸したことは記憶に新しいところです。
インサイトの目的も火星の地質を知ることで地球や太陽系の謎に迫ることにあります。
熱気球による地質調査――金星上空の雲は地球と似ていた
 Image Credit:NASA/JPL
Image Credit:NASA/JPL
NASAのジェット推進研究所は、金星の地震活動を熱気球を使って空から観測するという提案をしています。
そのような試み――金星の地震活動を観測することやそれを空から行おうとしていること――は初めてのことです。
しかし二酸化炭素で覆われている金星に熱気球を浮かべることなど、そもそも可能なことなのでしょうか。
実験チームのメンバーであるSiddharth Krishnamoorthy氏は「金星の地質を調査できる気球についてのアイデアはたくさんある」といいます。
これまでの探査機の調査によって金星の大気の層が厚いことはわかっています。
この層が地表での気圧を押し上げることで探査機のほとんどが地上に到達する前に破壊されるか、到達しても今度は高熱により機能を停止してしまいます。
しかしマゼランのデータによると、高度50kmから上は地球とほぼ同じ気圧であることがわかっています。
もしこの層に気球を浮かべることができれば地球で実験したデータをあてはめることができます。
2018年の12月19日に行われた実験では、ネバダ州の静かな砂漠が用いられました。
アメリカエネルギー省の研究者が地下300mで50トンの化学爆発を起こすと、マグニチュード3~4の人口地震が起きました。
上空にはヘリウムで満たされた実験用の気球が浮かんでいます。
 Image Credit:JPL/NASA
Image Credit:JPL/NASA
気球は地震が起こした気圧の変化を測定しつつ、超低周波の波や人間では聞き取ることのできない音響振動を検出することに成功しました。
Krishnamoorthy氏は「これがすぐに金星の地質調査につながるわけではないが、困難な地表調査に代わる新しい方法になるかもしれない」と述べ、最近地震が活発になっているオクラホマ州の上空に気球を移動させ、さらなる実験を続ける予定だと語りました。
金星探査の未来
金星の上空には「スーパーローテーション」と呼ばれる超高速で流れる風が存在しています。
これは金星の自転速度よりも早い秒速100mで吹く風で、なぜそのようなことが起きるのかは今のところわかっていません。
惑星の自転速度の60倍もの速度を持つ風の存在はこれまで知られていなかったため、このスーパーローテーションの謎を解くことは金星探査における一つの目標になっています。
そして現在この謎を解明するために金星上空でデータを収集しているのがJAXAの金星探査機「あかつき」です。
 あかつきと金星 Image Credit:JAXA
あかつきと金星 Image Credit:JAXA
あかつきは日本の探査機として初めて地球以外の惑星軌道に投入された探査機で、金星の気象を解明するために活動しています。
つい最近には高性能の赤外線カメラを使った調査から、雲の中に巨大な筋状構造を発見しています。
あかつきは、この筋状構造が地球の温帯低気圧や移動性高気圧をもたらす現象と同じであることを世界で初めて解明しています。
あかつきはスーパーローテーションの解明のために金星に向かった探査機ですが、その最終的な目的はこれまで各国が打ち上げてきた探査機のものと同じです。
それは、金星を知ることが地球や太陽系さらには宇宙を知ることにつながる、というものです。
地球が特別な星だと理解すること――それは未来へとつなぐ人類の希望です。
宇宙とか星とかあまりにも壮大すぎて現実味がわきませんが、世界の研究者や探査機が他の星を理解しようとしているのをみると、人間の悩みなんかちっぽけなものなんじゃないか、と感じてしまいます。
今後も稼働予定のあかつきはさらなる新しい発見をもたらしてくれることでしょう。
そしていつの日か金星の上空に色とりどりの熱気球が浮かぶことにも期待したいと思います。

ゆらゆら~♪気球の旅もいいね~♪

たまには上から見るのも悪くないな

……だめだ、酔いそう

あれ……なんか下がってきてる……って燃料が!

た、助けて~!落ちる~!……うっ、気持ち悪い……
金星調査の歴史と未来、そしてNASAの熱気球の話題でした。
References,sciencemag,JAXA